子どもと一緒に学ぶやさしい金融教育
💬はじめに:おかねって、なんだろう?
「おかねって、なんで必要なの?」子どもからそんな質問を受けたことはありませんか?
大人にとっては当たり前の「お金」も、子どもにとってはちょっと不思議な存在。
このブログでは、お金を**「ありがとうを形にした交換の道具」**として、家庭・心理・倫理・経済の4つの角度からやさしく考えていきます。
💛新作動画を公開しました!子どもと一緒に考える、やさしい金融教育シリーズ第1弾🎥「🌱おかねは『ありがとう』を運ぶチケット」➡️ YouTubeで見る(もも先生の児童図書館チャンネル)
🧠1. 経済の視点:おかねは「信頼のバトン」
昔の人たちは「物々交換」で生活していました。
でも、「魚をあげるから服をちょうだい」と言っても、相手が魚をいらないと交換できません。
そこで生まれたのが「お金」です。お金は「価値を預ける道具」であり、みんなが信頼して使うからこそ価値がある。
> 💡つまり、お金は“信頼”の上に成り立つ「社会の約束」なんです。
💓2. 心理の視点:おかねは「気持ちのリトマス紙」
お金を通して、子どもは**「ほしい気持ち」と「がまんの気持ち」**を学びます。
100円玉ひとつを握りしめて駄菓子屋に行く――その中で「どれにしようかな」と悩む時間こそ、心の成長の瞬間です。
> 💬お金は、子どもの「自分で決める力」を育てる先生。
おこづかい帳をつけることは、ただの記録ではなく、自分の「気持ちの見える化」なんです。
🌿3. 倫理の視点:おかねは「やさしさをつなぐ橋」
お金は“使い方”で価値が変わります。誰かを笑顔にするために使えば、それは「やさしさの道具」。
逆に、自分だけのためだけに使えば、「孤立の道具」になってしまうことも。
> 💡お金は「ありがとう」と「ごめんなさい」を運ぶ力を持っています。
募金やプレゼント、お手伝いへのお駄賃など、お金を「ありがとうの循環」に使う体験を、ぜひ家庭で共有しましょう。
🏡4. 家庭教育の視点:おかねは「日常の会話」から学ぶ
「お金の話=タブー」と思われがちですが、
実はお金こそ、家庭で自然に学べる最高の教材です。
スーパーで「このお菓子は100円。こっちは120円。どっちを選ぶ?」そんな日常会話が、最高の金融教育になります。
> 💬親子の会話が「おかねの授業」。感謝・選択・思いやりを学ぶ時間です。
🌈まとめ:「おかね」は“ありがとう”の道具
おかね=数字やモノではなく、人の気持ちを形にした「ありがとうの道具」。
お金を学ぶことは、「人とのつながり」を学ぶことでもあります。
そして、それを教えられるのは、学校ではなく“家庭”です。
> 🌸今日のおかねの一言「おかねは、ありがとうを運ぶチケット」

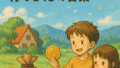

コメント